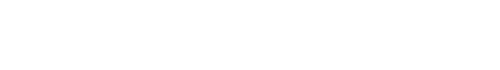ミッション
算数を制するものは受験を制す!
受験で試されること
中学受験であれ、高校受験であれ、大学受験であれ筆記試験で試されるのは「論理的思考力」と「暗記」のみ、この二点です。
他の力(創造力や感性、表現力、独創性、胆力、忍耐力、コミュニケーション力など)は試されません。
非常にシンプルなことですが、受験に勝ち抜くにはまずこのことを理解しておかないといけません。
そして、受験で大きな差がつきやすいのは論理的思考力を問う問題であることも。
算数と論理的思考力
算数は論理的思考力を養う最も重要な科目です。
暗記は、例えますと、栓の抜けたお風呂に、流れ出るより多くの水を入れて溜めていくような作業です。作業の量が大事になります。
一方、論理的思考力はマッチ棒のような部材で構築物を組み立てていく緻密な作業のようなものです。
小さな構築物から大きな物へと倒れないように組み立てていくようなイメージです。
作業の方法、正確さが大事になります。
小学生高学年はこの構築物の土台、基礎の部分を築く最も重要な年齢なのです。
ここで間違って組み立てられてしまったり、もろい構築物であったなら、その上に大きな構築物を組み立てることはできなくなります。
将来必ず論理の構築に躓き、膨大な時間を必要とするようになります。
論理的思考力を養うには講師の力が不可欠
子供たちが初めて出会う論理や理解できなかった論理、誤って理解してる論理を正しく理解させるには講師の助けが必要不可欠です。
特に小学生では何が理解できていないかそれすらも自分自身でわからない、また説明することもできないことがほとんどです。
そこでそれを見極めることができる講師の力が要求されます。
そして理解できた論理を元に演習を繰り返し、頭に論理の回路を定着させる。
子供の力を見さだめて、適した演習を与えることにも講師の力量が問われることになります。
そして徐々に、より複雑な論理へと導いていく。
非常にシンプルですが、これの繰り返しにより、子供の持つ論理力の次元を徐々に上げていきます。
小学校の算数教育の問題点
中学校三年間で学ぶ数学の内容は非常に薄っぺらく、普通の子であれば小学校5~6年の二年間でほとんど習得できる内容です。
徳島県立高校の数学の入試問題と難関と言われる私立中学校の算数の入試問題を比べた場合、はるかに後者の方が難しいということをご存知でしょうか?
(実際に問題にならないほどの難易度の差があります。)
そして難関中学を目指して学習してきた子たちは、中学校の数学の原則はほとんど理解してしまいます。
中学の数学の原則を理解するのは柔軟な頭脳を持つ小学校高学年の方が容易く短い時間でできるのです。
さらに問題なのが、中学校では少なくともある程度は専門的に勉強してきた先生が教えますが、小学校ではそうではありません。
この大切な時期に小学校で算数を教えるのは残念ながらエキスパートではありません。
むしろ、数学や算数が苦手な先生のほうが多いのではないでしょうか?
もし英会話もろくにできない小学校の先生が英語を教えたとしたら?
想像してください。基本的なところで誤った発音や使い方が身についてしまい、後々まで引きずってしまうことでしょう。
算数、数学も同じです
。本来は小学校高学年であれば算数、数学の専門の先生が正しく教えるべきだと私は思っています。
徳島県の大学合格実績の崩壊
東大 18人
京大 36人
阪大 21人
この数字は昭和47年の城南高校ただ一校の合格実績です。
それが近年はどうなっているか?
3大学合わせて、誤差は多少ありますが、全県下で15~20人程度になっています。
(令和5年度は東大3人内現役1人で全国最下位だそうです。)
旧帝大と早慶の難関大学だとさらにひどい結果となっているようです。
(少子化は関係ありません。大学の定員はほぼ変わっていないのですから)
昭和47年と同じ割合で徳島県にもたくさんの優秀な子供たちがいるはずです。
その子供たちがより大きく羽ばたくのを、徳島県の教育が、そして子供の環境が阻んでいる結果となっているのです。
崩壊の原因
原因は一つではなく複合的なものだと考えています。
徳島県の高校受験は競争が非常にゆるい。
高校の進学指導で国公立大学の推薦入学を推し進める。
などです。
しかし別にさらに大きな要因があると私は考えています。
中学、高校は徳島県でもそれなりに塾は充実しており、都市部とも変わらない環境が整っています。
そして通塾率も高いようです。
では小学校はどうかというと、これはあまりにも差が大きい。
他府県、特に都市部との差が非常に大きいのは小学校高学年の学習なのです。
都市部においては中学受験が熾烈な競争を生み、難関中学を目指す小学校高学年の生徒は毎日5時間以上、
休日には10時間以上勉強することなど当たり前のことなのです。
そのことがいいことか悪いことかの議論はここでは置いておきます。
ただここで付いた論理的思考力の差を中学以降に埋めるのは至難の業であるという事実をお伝えしないといけません。
小学校高学年において算数を鍛錬するとしないでは、中学校以降の論理の理解の確実性だけでなくスピードも全く違ってしまいます。
すなわち、小学校高学年で鍛錬した人とそうでない人が中学生以降に同じ勉強量をこなすとしたならば、大学受験まで加速度的に差は広がり続けるということになります。
蛇足になりますが、
こうやって熾烈な競争を勝ち抜いて最難関私立中高一貫校に入学した人たちはその後も厳しい勉強を続けているのでしょうか?
私の知る限り答えは「否」です。
灘や開成では、東大理三を目標にするとか、根から勉強が好きとかの例外を除けば、
ほとんどの生徒が中一から高三の春まで部活や趣味、学校行事に没頭しており、その勉強量は徳島の進学校より少ないと思います。
彼らが本格的な受験勉強を始めるのは、灘高でも開成高でも学校行事が終わる高三の5~6月くらいからです。
そのあと僅か10ヶ月足らずで多くの生徒が東大合格ラインまで仕上げてくるのです。
このような離れ技ができるのも、小学校高学年で自らの論理的思考力を限界まで鍛え上げているからだと私は思っています。
灘高から東大に入り卒業した人に「最も勉強したのはいつ?」と聞くと、ほとんどの人が「小学校高学年」と答えたという記事をどこかで見た記憶があります。
ミッション
このように小学校高学年という一生に一度しかない生涯最高の頭脳を持つ時期に培った高い論理的思考力は、その人の一生の宝物となるのです。
その宝物を与えて、徳島の子供たちの将来の可能性を広げることこそが私共のミッションだと考えています。
追記
前述通り、一般的に徳島の子供たちは小学生の学習で出遅れています。
徳島の大半の子供たちは公立中学→公立高校と進学します。
この過程でいつその遅れを取り戻すことができるのでしょうか?
取り戻すことができるとすればそれは中学の3年間です。
数学は高校から学年が上がるにつれ内容は急速に難しくなり、それを習得するのにも時間がかかるようになります。
高校3年生で難易度の高い数学Ⅲを履修しながら並行して大学受験勉強をするのはまず無理です。
難関大学を狙うならば遅くとも高校2年生で数学Ⅲをマスターしておかなければなりません。
できれば高校2年生の夏休みまでにマスターしておきたい。
ところが中学で習う数学はあくまで義務教育ということで大変簡単で薄っぺらい。
難関大学を狙うような優秀な子であれば習得するのに1年はかかりません。(頑張れば半年程度)
この期間に先取り学習をすることが重要であり、大学受験も決めてしまいます。